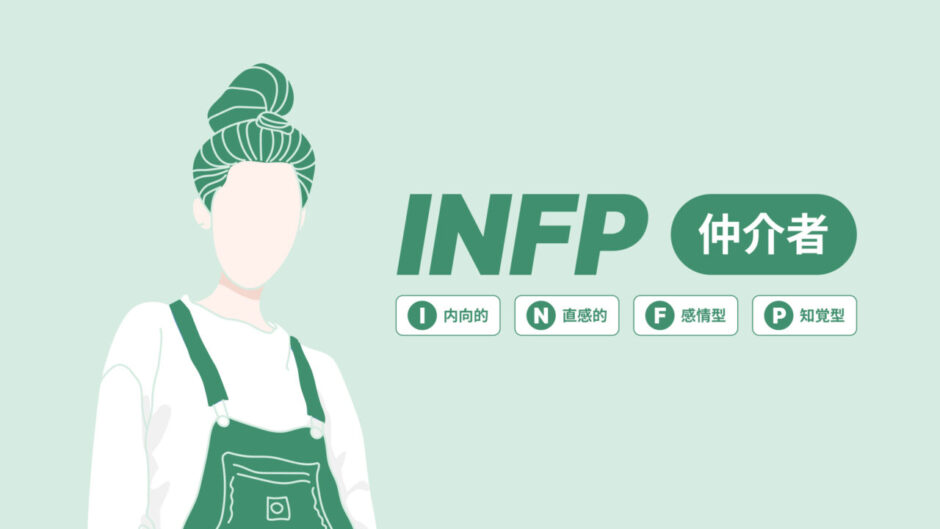RANKING相性
![]()
INFP(仲介者)
相性最高!
- 1位:ENFJ(教導者)
- 2位:INTJ(建築家)
- 3位:ENTJ(指揮官)
- 4位:INFJ(提唱者)
- 5位:ENTP(討論者)
- 6位:ENFP(冒険家)
- 7位:INTP(論理学者)
- 8位:ISFJ(擁護者)
- 9位:ESFJ(援助者)
- 10位:INFP(仲介者)
- 11位:ISFP(芸術家)
- 12位:ISTP(巧緻家)
- 13位:ESTP(起業家)
- 14位:ESFP(エンターテイナー)
- 15位:ESTJ(管理者)
「なぜ私は過去に心が縛られるの?」—INFPさんとSi(内向的感覚)成長のはじまり
「昔の失敗、なかなか忘れられない」「ときどき意味もなく懐かしい気持ちが押し寄せて動けなくなる」「みんなみたいに流れに乗れない自分がもどかしい…」
そんな風に、自分の“感覚や記憶”が人生や決断にじわじわ影響していること、ありませんか?
実はそれ、 INFPの「第三機能」——Si(内向的感覚)のしわざかもしれません!
MBTIの性格タイプの中でもINFP(仲介者)は、“夢見る理想主義者”として知られる存在。新しい価値観や希望を大切にし、人の気持ちに敏感で、独特な世界観を持っています。
けれど同時に、ふとした時に“過去”や“体験したこと”に心が縛られたり、「小さな違和感」や「なぜかわからないモヤモヤ」に戸惑ったりすることが多いタイプでもあるんです。
実際に私のもとには、こんなINFPさんたちからの声がたくさん届きます。
> 「新しいことに挑戦したいのに、昔の小さな失敗ばっかり思い出して、足がすくんでしまいます…」
>
> 「周りの人は“今”を楽しそうに生きてるのに、私はどこか『昔の自分』や『過去の思い出』に引っぱられがち。どう向き合えばいいの?」
>
> 「“自分らしさ”を大切にしたいけど、内向的感覚(Si)の特徴ってどんなもの?成長させる方法は?」
みなさんも、思い当たることありませんか?
この記事では、「INFPにとって、なぜSi(内向的感覚)は扱うのが難しいのか?」
「どうすれば、Siの魅力を“自分の強み”へと変えられるのか?」
そんな《モヤモヤの正体》とその改善法を、MBTI性格診断の専門家として、最新心理学のエッセンスも交え、やさしく(そして元気に!)ご紹介します!
そう!INFPの第三機能Siは決して「足かせ」や「苦手意識」だけの存在ではありません。
正しく理解し、少し工夫するだけで——INFPの優しさや直感力が、現実世界でも“確実な力”として花ひらく、スーパーな「味方」になるんです。
みなさんの悩み・モヤモヤ・自己否定が、今日で“過去のもの”になりますように。
いっしょに「INFP×Siの魅力開花ロードマップ」——今、出発しましょう!
—
この記事でわかること
この記事はこんな方にピッタリ!
– INFPタイプとして、どうして「昔の記憶・体験」に振り回されやすいのか理由を知りたい方 – Si(内向的感覚)がなぜ“第三機能”としてINFPに特別な影響を与えるのか、その特徴・発達過程を知りたい方 – Siを「足かせ」じゃなく「味方」に変え、自分らしさをパワーアップする具体的な方法を探している方 – 心理学や最新の研究にもとづいたINFP成長のヒントがほしい方 – 日常で役立つ「Si克服・成長のための行動プラン」「すぐにできるセルフワーク」のやり方を知りたい方
この記事を読めば、
– INFP特有の「過去に縛られがち」「小さな違和感に悩む」理由がスッキリ理解できる – Siという“宝もの感覚”を活かして「どんな時もブレない自分」になる道筋がわかる – だからもう、「INFPって面倒くさい性格なのかも…」なんて思う必要がなくなります♡
読者さんが「この記事に出会えて本当に良かった!」と思えるよう、ていねいに、そして楽しくお届けします♪
—
INFPの第三機能Si(内向的感覚)とは?その基礎からわかりやすく解説!
INFPタイプの独自性とメイン機能「Fi」との関係
まず、「INFP」タイプにはどんな特徴があるのか整理してみましょう!
– I(内向):自分の内側の世界、心理的な充実が大切。外よりも自分のお部屋が好きな傾向。 – N(直観):物事を全体や未来・意味でとらえる。小さな違和感にも鋭いアンテナ。 – F(感情):人の気持ち・価値観・理想を何より大事にする。“優しさ×理想主義”のハイブリッド。 – P(柔軟):きっちり計画より、その時の流れや「ピンとくるもの」に身を任せるタイプ。
INFPのメイン機能(最も得意分野)は「Fi(内向的感情)」。 —「私は何のために生きる?」「どんな価値を守り、誰に優しくしたい?」——こういう深いテーマをよ~く考え、ブレない信念を心の真ん中に持っています。
「みんなに合わせよう」とは思わないけれど、相手の心の背景や成長をすごく大事にする、そんな“理想の仲介者”なんです。
Si(内向的感覚)ってなに?専門用語をやさしく!
では、タイトルにもある「Si(内向的感覚)」とはなんでしょう?
→ Si(Introverted Sensing)……「過去の体験や五感の記憶」から信念や安心感を作り出す力!
たとえば…
– 「このお店の匂い、なんだか懐かしい!」 – 「前にこのパターンで失敗したから、同じミスをしないよう注意しよう」 – 「自分らしさは、昔からこうやって守ってきた」
こうした「過去」と「今」「自分の五感」をつなぐ感性、それがSiなのです。
MBTI®の機能配置では、INFPは
- Dominant(第一機能):Fi(内向的感情)
- Auxiliary(第二機能):Ne(外向的直観)
- Tertiary(第三機能):Si(内向的感覚)
- Inferior(劣等機能):Te(外向的思考)
INFPは、第三のサブ機能として「Si」を持っています。この位置づけが、独自の“モヤモヤ”や“安心感”につながりやすいポイントなのです。
—
INFPの第三機能Siが引き起こす「モヤモヤ」の正体
なぜINFPは「過去の記憶」にとらわれやすい?
心理学的にみても、「第三機能」というのは思春期後半から20代~30代にかけて、意識にのぼりやすくなるとされています(Jung, 1921; Beebe, 2016)。
INFPの場合、Fi(感情)やNe(直感)が自然と働く一方で、「Si(内向的感覚)」が“無意識のクセ”として現れやすい傾向があるんです。
Siは、自分が「安心できるもの」「よく知っているもの」「なじみのある経験」から学び、そこに帰りたがる性質があります。
そのため、INFPタイプの人はこうなりがち——
– 新しいチャレンジの前には、いつも「昔の失敗体験」や「不安だった記憶」を鮮やかに思い出して足がすくむ。 – なにかちょっとした違和感やミスがあると、「またダメだった」と感じてしまいがち。 – 昔あった“楽しかった思い出”を理想化しやすく、現実と比べて落ち込んでしまうことも。
第三機能の「Si」は、INFPが本来持つやさしさや理想主義とミックスされ、「過去に縛られやすい」「安心できる自分の世界にこもりがち」という側面として現れるのです。
どうして「日常の小さな違和感」に敏感なの?
Siがうまく働かないと、INFPは「過去のパターン」や「自分の感覚」に頼るあまり、ちょっとした変化へのストレスや違和感にすごく敏感になります。
– いつも座っていた場所が変わるだけで落ち着かない! – 食べなれないメニューにチャレンジすると、「これでいいのかな…」と不安。 – 人間関係で、「昔このパターンで失敗したから…」と新しい出会いを避けてしまう。
これは“外の変化”にうまく適応しきれないことの現れ。INFPのやわらかい感受性×Siの「安心なもの大好き」が、逆に“制限”や“不安”をつくってしまう瞬間です。
心の背景には「安全基地」願望が
でも、これって本当は“悪いこと”でしょうか?
いいえ!
実は、最新の心理学研究(例えばMary Ainsworthの愛着理論)でも、「心に安全基地がある人ほどストレスや変化に強くなれる」といわれています。
INFPのSiは「自分らしさの原点」「安心できる思い出」「自分だけの宝物体験」を大事にし、
それを“心の立ち戻り先”として活用できれば、めちゃめちゃパワフルな「味方」になるんです!
—
最新心理学&統計で読む、INFPのSiの発達と克服メカニズム
1. 発達段階ごとのSiの「あるある」現象
MBTI理論と近年の研究(John Beebe, 2016; Nardi & Joel Mark Witt, 2021など)によると、
INFPのSiは年齢や経験と共にこう変化します。
– 10代〜20代前半:「なんだかわからないザワザワ」期
→ 直感や感情で行動する反面、人と違う自分/過去の小さな失敗に心が縛られてしまう。
→「自分だけ浮いてる気がする」「友だちの輪になじめない」と感じやすい。
– 20代後半〜30代前半:「過去に戻りたい(or閉じこもり)」期
→ 独自のぬくもり体験や好きな世界観に強くこだわり、“新しい経験”よりも“今までの安心”を優先。
→「前も失敗したし…」「自分なんてまたダメだろう」と挑戦が怖くなる。
– 30代〜40代以降:「思い出を力に変える」成長期
→ Siの「安心・経験の知恵」を活かして、内省や自己成長・人のサポートに目覚める。
→「私だからこそできる、人の痛みを知る力」として開花し始める!
このように、Siの扱い方が変わることで、「自分らしさ」の幅や生き方の広がり方に大きな違いが出てくるんです。
2. なぜ「第三機能」は“葛藤”と“成長”をもたらすのか?
第三機能(Tertiary)は、第二機能ほど使いこなせず、でも第四機能(最下位)ほど苦手でもない——
まるで「ちょっと手が届きそうなのに、まだ不器用な楽器」のようなもの。
そのため、
– 無意識に出るクセを意識すると“なんか恥ずかしい・もぞもぞ”な気分になる – 「まだうまくできていない自分」への自己嫌悪が生まれやすい – どうせなら「別に大事じゃない」と無視したくなる
でも、ここを「成長機会」として丁寧に使うほど、
INFPの“人と違う輝き”がドンドン強まっていく、という仕組みです!
3. 統計でも見える!INFPの「過去思考」とポジティブ回路の重要性
MBTIコミュニティや性格診断の統計データ(MBTI® Manual 4th ed./2018)によると、
INFPの約7割以上が「過去にとらわれやすい」「慣れていないことへの不安が大きい」と回答しています。
一方で、「自分の体験を生かして人の相談にのる」
「昔の思い出から学びを見つけて、前向きな自己成長につなげる」
と回答したINFPほど、「自尊感情」「幸福度」「自己決定感(やりたいことを自分で選びやすい力)」が明確に高いことも判明!
→ Siをうまく活用できるINFPは、人生の充実度まで違ってくる!
これが科学からの心強いエビデンスです。
—
INFP(仲介者)がSiを味方につけて成長する7つのステップ
ではここから、INFPタイプがSiを「苦手」から「強み」に変える7つの成長ステップを、実例つきでご紹介します。
ステップ1:「過去の体験」にレッテルを貼りすぎない
【やりがちなNG例】
「前も同じことで失敗した=私はもうこれが苦手なんだ」
「うまくいかなかった=またダメに決まってる」
【おすすめセルフワーク】
→「失敗した経験の“景色”をひとつひとつ書き出してみる」
“感じていたこと”より、“どんな匂いや色、場所だった?”など五感に目を向けてみて。
→ 実際は「当時の環境が合わなかっただけ」だった、など新しい気づきが見つかることが多いんです!
ステップ2:「なじみのあるもの」を“自分らしさの基地”にする
INFPは「好きなもの」や「お気に入りの空間」をとても大事にします。 ここでは「安心感」を否定せず、逆に“心のパワースポット”として意識づけましょう!
【具体例】
– 古いノートやお気に入りのマグカップを、考え事のときのお守りにする
– 好きな香りや音楽で「自分だけの安心ゾーン」をつくる
– 「気持ちが落ち込むときはこの場所!」という“定番スポット”を作る(おうちの窓際でもOK!)
ステップ3:「思い出」と「今の自分」を積極的につなげ直してみよう
【やりがちなNG例】
→「昔はああだった、今は違う…」と過去との違いばかり気にして現状否定
【おすすめ実践ワーク】
– 昔好きだったことと、今できる小さなことを組み合わせてみる
– 例:「子供の頃好きだった塗り絵を、“大人の塗り絵”でやってみる」
– 「なぜ今の私にはこの思い出が大事なんだろう?」と自分に問いかけて、小さな成長ポイントを日記にメモ
ステップ4:新しさへの“ちょい足し体験”でSiを活性化!
INFP✕Siは「ガラッと変わる」より「ちょっとだけ新しい」チャレンジが効果大!
【具体的行動例】 – いつもと違う道で帰宅してみる(景色の中に新旧を見つける遊び感覚で) – 気になるカフェで「見たことないドリンク」を一杯だけ頼んでみる – “安心のパターン”を少しだけアレンジして毎日の小さな冒険を増やす
ステップ5:「五感の記憶」をいま一度“味方”にする
INFPは言葉にするのが苦手な“温もり記憶”や“香り、風、音”の記憶力がピカイチです!
これを新しい学びや癒しに積極的に使いましょう。
【おすすめワーク】 – 好きなシーン(景色・音・匂いなど)で“気分ノート”をつくる – ちょっと心が疲れた日は、「過去の素敵な感覚を意図的に思い出す時間」を持ってみる
ステップ6:「人と比べず、じぶん基準」で振り返ろう
Siは「自分のやり方、過去の経験」にフォーカスする性質。人と比べても意味がありません。
【おすすめ習慣】 – 毎週、ちいさな「今週の発見!私だけのベスト3」を書き出してみる – 「昔よりここが成長したな」「あのときの自分より○○できるようになった」と、他人軸ではない“自分基準”の成長記録をつける
ステップ7:Siの「よかった!」を“人の役立ち”に切り替えよう
最後に!Siの真骨頂は「経験が人の役に立つとき」。例えば—
– 自分の“乗り越えた悩み”を友だちにシェアしてみる – 誰かが同じことで悩んでいたら、「私はこうだったよ」と優しく伝えてみる
この「自己開示」と「経験のシェア」で、Siの“宝物”がより輝き始めます!
—
Siを活かして「生きやすい私」でいるコツ—よくあるシチュエーション別アドバイス
仕事・学校で「新しいことが不安」「慣れない環境が苦手」なとき
– はじめての場所や仕事でも、「最初に安心できそうなポイント」を探してみましょう。
例:お気に入りの文房具を持ち歩く/以前と変わらない習慣を取り入れる
– 新しいチャレンジに“昔の体験”を持ち込まず、「一度ためしてみて嫌だったらやめればいい」と小さな実験感覚で向き合うのが◎
恋愛・人間関係で「昔の失敗」ばかり思い出すとき
– 「過去の傷」は、“今の私”への注意サイン。決して悪者じゃありません! – 自分が大切にしてきた“理想”や“感覚”を、今の出会いや関係性にも大事にできるかよく考えてみて。 – 「理想と違ってた」「また傷つくかも」そんな不安が訪れたら、それでも「まずやってみる」「言葉にしてみる」ことで新しい体験がはじまります。
自己肯定感が下がったとき・自信を無くしたとき
– 「昔の自分より1ミリでも進んだ」と肯定するセルフグッズ(日記・フォトアルバム・お守りなど)を活用 – 五感を通じた心地よい体験(自然の景色、肌ざわりの良いもの、おいしいごはん)で心をリセット
—
INFPとSiをめぐる「ありがちなお悩み」Q&A
INFPのSiと「過去のトラウマ」ってどう向き合えばいい?
A:
Siは「過去の痛み」も「大切な思い出」も強く記憶する分、トラウマ体験に敏感。もし昔の失敗や傷にとらわれて動けないときは、
まずその体験を“今あるもの“として書き出すワークや、信頼できる友人・カウンセラーへ話してみることで、徐々に手放せます。
Siは「過去そのものではなく、それを“どう今に活かせるか”」という視点転換が鍵ですよ!
Siを強化すると“現実主義”になってINFPらしさが薄れませんか?
A:
心配ご無用です! Siを強化することで「安心感」「自己基盤」「本当の意味での“自分らしさ”」が太く育つだけ。
Ne(直観)やFi(理想主義)を絶やすことはありません。むしろ、「夢や理想を“現実の手触り”に変えられる柔軟さ」がパワーアップします。
Siは、INFPらしい「やさしく独特な世界観」を“より豊かにする味方”と考えてください。
INFPがSi克服のために避けたい「落とし穴」は?
A:
一番よくある落とし穴は、「Siを“無理やり変えよう”とすること」です。
INFPは本来、「安心」「マイペース」「自分らしいリズム」が大事な性格。過去や習慣を“むしろ大切に活かす”ことこそSi成長の正しい道。
焦らず、ちいさな冒険や新しい体験を“自分のタイミング”で、これが一番の近道です♡
—
まとめ:Siは「自分を守るおまもり」から「世界を広げる翼」に変えられる!
INFP(仲介者)にとって、Si(内向的感覚)は“過去”“安心”“五感”を軸とした大事なサブ機能です。
最初は「過去に縛られる」「いつも不安…」に感じても、その正体を知り、やさしく育てることで
INFPだけが持つ「夢」「優しさ」「人と違う独自性」が、大きな現実的な力になるんです。
INFP×Siは、“安全基地”“宝物の思い出”をエネルギー源に、「自分基準」で一歩ずつ前進できる最強の武器!
今日から、あなたらしい歩み方で「第三機能Si」を、もっと心強い味方へ進化させましょう。
この出会いが、みなさんの“理想のわたし”への新しい第一歩になりますように♡